【薬学部】定期試験を余裕でパスする方法

・試験には合格できるけどいつも合格点ギリギリ
・なぜかいつも単位を落としてしまう
こういった方は多いと思います。
これらの原因として考えられることは、
・勉強が続かない
・勉強方法が間違っている
・過去問分析ができていない
この3点です。
僕も大学2年生までは、必死で勉強したのに再試験になったり定期試験に合格しても点数が取れていないことが多々ありました。
でも、上記3点ができるようになってからは余裕を持って定期試験に合格できるようになりました。
今回の記事では、
・勉強のやる気・モチベーションをUPする方法
・余裕を持って試験に合格するための方法
・過去問分析の流れ
を解説していきます。
CBTや国家試験にも役に立つ内容なのでぜひ最後まで読んでみて下さい。
勉強方法は自分に合ったものを見つけるまでに時間がかかりますが、一度身に付けてしまえばどんどん勉強が楽になります!
こちらの記事では、定期試験に役立つ参考書を紹介してるので参考にしてみて下さい。

「勉強をする理由」があれば勉強は続けられる!
「そもそも勉強のやる気があったらとっくに勉強してるし、こんなに勉強に困ってないよ」って思いませんか?
皆さんが勉強に対してやる気がなかったりモチベーションが保てなかったりするのは、勉強をする理由がないからです。
逆に言えば、勉強をやる理由があれば勉強のやる気は続きますし、継続も簡単になります。
正直、試験に受かりたいとか薬剤師になりたいだけだと動機としては弱いです。
それで勉強が続いているなら多くの薬学生がやる気やモチベーション問題で悩んでいません。
重要なのは、試験に受かったら(受からなかったら)どうなるのか、薬剤師になれたら(なれなかったら)どうなるのかなどをしっかり考えて自分なりの答えを出すことです。
そこでここからは勉強をやる理由について解説していきます。
ぜひ、自分の勉強をやる理由を見つけるヒントにしてください。
そもそもなんで薬剤師になりたいのか考える
まずなんで自分は薬剤師になりたいのかを考えるといいです。
・1人でも多くの患者さんを救いたいから
・給料が高いから
・職が安定してるから
・社会的地位が高いから
・モテたいから
など何かしら1人1人薬剤師を目指している理由があるはずです。
これをしっかり突き詰めて考えていくと勉強をする大きな原動力になります。
ここでの理由は不純でもいいのでとにかく自分にとって納得できる理由を探しましょう。
薬剤師を目指したきっかけについてもう少し知りたい方は下の記事も参考にしてみて下さい。

今の勉強が何の役に立つのか考える
例えば、
・物理⇒MRIや放射線治療
・化学⇒薬理作用や副作用の理解
・生物⇒病態や薬理学の理解
・衛生⇒病気の予防
・薬剤⇒薬の代謝や飲み合わせ
・法規⇒日本がどんな仕組みで医療が行われているのか
など、今自分が勉強していることが何の役に立つか考えると意外とモチベーションになったりします。
なんで勉強しているか分からないままだと勉強のやる気は起きません。
過去に化学が臨床で役に立っている例を記事にしたので興味がある方読んでみて下さい。
講義や国試の参考にもなります!
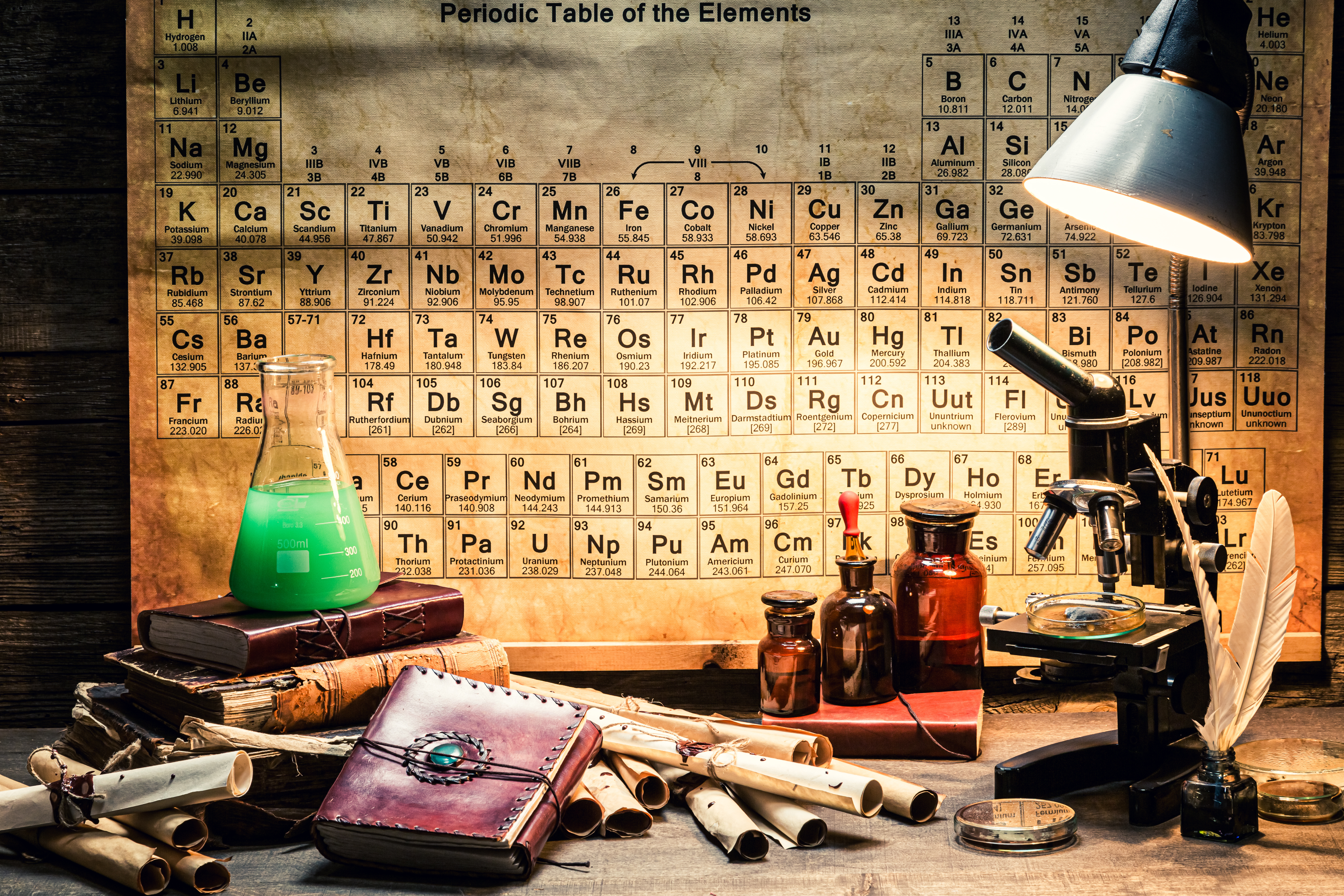
試験に落ちたらどうなるのかを考える
親に学費を払ってもらっている人が前提ですが、試験に落ちて留年したり国家試験がダメで浪人したらたら親に迷惑がかかりますよね。
例えば、学費が年間200万円かかるとしたら留年してしまうと親に200万円余分に学費を払わせてしまうことになります。
国試をもう一回受けるために1年で100万円かかる予備校に通うと親に出費させてしまいます。
100~200万円あったら旅行や車、恋人へのプレゼントなど欲しいものは大抵手に入る金額です。
こうならない為にも普段からしっかり勉強をして親に迷惑をかけないようにしましょう。
ストレートで卒業して一発で国試合格することも親孝行の一つだと思います。
余裕を持って試験に合格するための方法
冒頭でもお話しましたが、試験で点数が取れない主な原因はこの3点です。
・勉強を始める時期が遅い
・勉強法が誤っている
・過去問分析ができていない
ここからはこれらの原因の対処法を解説していきます。
スケジュールを立てて勉強する
僕の周りもそうでしたが、スケジュール管理がしっかりできている人は成績もいいし旅行に行ったりして充実した大学生活を送っているイメージでした。
逆にスケジュール管理ができていないと
・いつ勉強を始めたらいいのか分からない
・ダラダラしてしまい、試験直前で焦る
・勉強が間に合わず試験で落ちる
みたいな事に陥ってしまいます。
こんな負のループに陥らないようにしっかり計画を立てて勉強しましょう。
いつから勉強を始めればいいかは分からないと思うので、最初は定期試験の1か月~1か月半前辺りを目安にスタートさせればいいと思います。
ここでもう少し直前でも大丈夫だと思えば、勉強開始時期をもう少し遅らせてもいいです。
その辺りは自分と相談しながら調整していきましょう。
簡単に試験前の勉強について流れを説明します。
試験1か月~1か月半前
・試験範囲をざっくり確認
・過去問分析
・問題演習
・やるのは暗記じゃなく理解する部分
(暗記しても忘れてしまうので効率が悪いです)
試験1~2週間前
・過去問見直し
・問題演習
・理解よりも暗記を徹底的にやる
「暗記」と「理解」に分けて勉強する
そもそも試験で点数をとるためには、まず知識のインプットをする必要があります。
インプットする内容は大きく分けて、
・「暗記」する内容
・「理解」する内容
の2つに分かれます。
そのまま暗記する内容をなんで?って考えてると時間の無駄になりますし、理解する内容をそのまま暗記しようとするといつまでも覚えられなくて苦労します。
なのでインプットする内容をこの2つに分けて勉強をすることで効率よく覚えられます。
暗記するものは人、法則、微生物の名前、薬の名前、病名などでざっくりいうとそのまま頑張って覚えるタイプの事柄です。
例を出すと
・長井長義
・熱力学第三法則
・黄色ブドウ球菌
・アスピリン
・シェーングレン症候群
などです。
この辺りを「なんでこの名前なんだ?」って考えるのもナンセンスなので素直に覚えちゃいましょう。
理解するものは、物事が起きた理由や背景などです。
いくつか例を挙げます。
・MRI検査時にニトログリセリン貼付剤を剝がさなければならない理由
・ピボキシル基をもつ薬が低カルニチン血症を起こすメカニズム
・なんで解糖系より電子伝達系の方がエネルギー効率がいいのか
・ノロウイルスにエタノールが無効な理由
・なんで腸溶剤をかみ砕いては服用してはいけないのか
・なぜ分子標的薬は通常の抗がん剤より副作用が少ないと言われているのか
などで、考えることが多いし大変なことがよく分かります。
実際に理解すべきことを理解できずにそのまま丸暗記になってしまい、結局試験で力を発揮できない方が多いと思います。
でも一度理解したことは、そのまま暗記した場合に比べて忘れにくいです。
なので時間はかかりますが、時間をかけてしっかり知識を定着させていきましょう。
過去問分析を徹底的にやる
・過去問分析って意味あるの?
・出た問題を覚えておきゃばいいんでしょ
と考えていると試験に合格する確率は下がってしまいます。
過去問はこういう問題が出ましたよっていう出題者からのメッセージなんです。
これを読み解かない手はないです。
例えば、ある試験で毎年トクホについて問われていたとします。
過去問分析を行わずにトクホに分野を飛ばして勉強してた人は痛い目を見ます。
逆に過去問をしっかり分析して対策を立てた人はトクホの問題は全部正解で無事に合格です。
もう1つ、過去問で出た問題をざっと見て試験に臨む方がいますがこれはNGです。
理由は、ほとんどの場合試験で同じ問題は出ないからです。
(国家試験では同じ問題はまず出題されません)
同じ問題が出ないのにどうして過去問分析をするのか?
その答えは、過去問分析を行うことでその試験の傾向と対策が分かるからです。
やり方は簡単です。
過去問で出題された範囲とその周辺を勉強する。
これをやることで、
・過去問と答えは同じでも聞かれ方が変わる問題
・過去問で出題されたところの周辺の問題
に対応することができます。
ただし、この作業にはすごく時間がかかるので試験の1か月以上前から過去問分析を始めるのがオススメです。
可能なら、新学期が始まってすぐに先輩や同級生から過去問を入手して講義を聞きながら過去問分析してもいいくらいです。
1年分だと試験の傾向が分かりにくいため、分析する過去問は定期テストなら2~3年分あると安心ですね。
勉強方法まとめ
・試験勉強は余裕を持って1か月以上前から始める
・「暗記」と「理解」を分けて勉強する
・過去問分析をして試験の傾向を知り、対策を立てる
まずはこのやり方を試してみて下さい。
勉強をする上での注意点
ここからは勉強する上での注意点を解説していきます。
100点を目指さない
いきなりですが、パレートの法則ってご存じですか?
80:20の法則とも呼ばれていて勉強の例でいうと、
ある科目の勉強に10時間費やした。
この科目を80点にするために2時間かかって、残り20点をとるために8時間かかった。
みたいなイメージです。
要するに80点の成果を得るためには2割の時間で良くて、残りの20点を取るためには8割も時間がかかるという考え方です。
ここで伝えたいことは、
テストで100点をとる必要はない
ということです。
定期試験や国家試験は100点を取らないと合格できないものではありません。
それに1つの科目で100点をとろうと勉強して他の科目を勉強する時間が無くなってしまっては本末転倒です。
100点を目指さず、80点を増やしていきましょう。
自分1人だけでやろうとしない
1人で黙々と勉強できるタイプならいいですが、全員がそういうタイプではないと思います。
そういう時は周りを巻き込みましょう。
自分1人だけで勉強するよりも友人などと教え合ったりできるので、周りのモチベーションアップもUPします。
ハチが勉強する上で大切にしていること
次に僕が勉強する上で大切にしていることをお話します。
この考え方は大学生の時から変わっていないので何か参考になる所があれば嬉しいです。
常に疑問を持つ
僕は常に疑問を持って、気になったことがあればすぐ調べるようにしています。
いくつか例をあげます。
・この反応は水酸化ナトリウムじゃなきゃだめなの?他の塩基でも良くない?
・ゴマペプチドってなんで血圧下げるの?
・なんでメトホルミンが糖尿病の第一選択なの?
・薬価とか別に覚える意味なくない?なんか意味あるの?
考え出したらキリがありません(笑)
でも、こういう考え方をしてきたので定期試験や国家試験で成績を残すことができたと思っています。
講義中にすぐ調べるのは難しいので、ノートや携帯にメモしておいて後で一気に調べると効率がいいです。
どうやったら忘れないかを考える
勉強ではその時覚えられても、試験の時忘れていたり思い出せなければ意味がありません。
そのため、常にどうやったら忘れないかなと考えながら勉強するようにしています。
具体的には、
・暗記なら語呂合わせを使う
・理解することなら白い紙一枚に全体像を書けるようにする、流れを人に説明できるようにする
などです。
これらの事を行うと試験当日にパッと思い出すことができますし、たとえ忘れても「思い出せる!」という余裕が生まれるのでぜひ参考にしてみて下さい。
勉強法に関するオススメ書籍
最後に、勉強方法に関するオススメの書籍を紹介します。
東大医学部在学中に司法試験も一発合格した僕のやっているシンプルな勉強法ー河野玄斗
この本の著者の河野玄斗さんってご存じですか?
東大医学部在学中に司法試験に合格した神のような人です。
本書は大学受験する方向けの本ですが、
・科目ごとの勉強方法
・勉強への考え方
・司法試験合格まで
などが書かれていて薬学生の方も勉強について学べる一冊になっています。
読んだら勉強が楽しくなる本だよ!
最短の時間で最大の成果を手に入れる超効率勉強法ーメンタリストDaiGo
メンタリストDaiGoさんの勉強法の本です。
薬学部なら聞く事も多い、エビデンスに基づいた勉強法がたくさん書かれています。
【科学的に効率が悪い7つの勉強法】
・アンダーライン
Amazon.co.jp: 最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法 eBook : メンタリストDaiGo: 本より引用
・語呂合わせ
・テキストの要約
・テキストの再読
・集中学習
・自分の学習スタイルに合わせる
・忘れる前に復習する
いきなりここから始まります。
勉強の常識を覆された気分ですよね(笑)
まとめ:勉強方法を実践して余裕も持って試験をパスしよう!
もう一度、勉強方法のまとめです。
・試験勉強は余裕を持って1か月以上前から始める
・「暗記」と「理解」を分けて勉強する
・過去問分析をして試験の傾向を知り、対策を立てる
他にも、
・勉強のやる気・モチベーションがない方は勉強をする理由を見つける
・100点ではなく80点の科目を増やす
・1人で勉強が行き詰まったら友人などと一緒に勉強する
などの考え方についても触れたので、勉強方法と考え方を組み合わせて点数を上げていきましょう!
勉強は時間がかかるけど、やった分必ず自分に返ってくるから楽しんで頑張ろう!






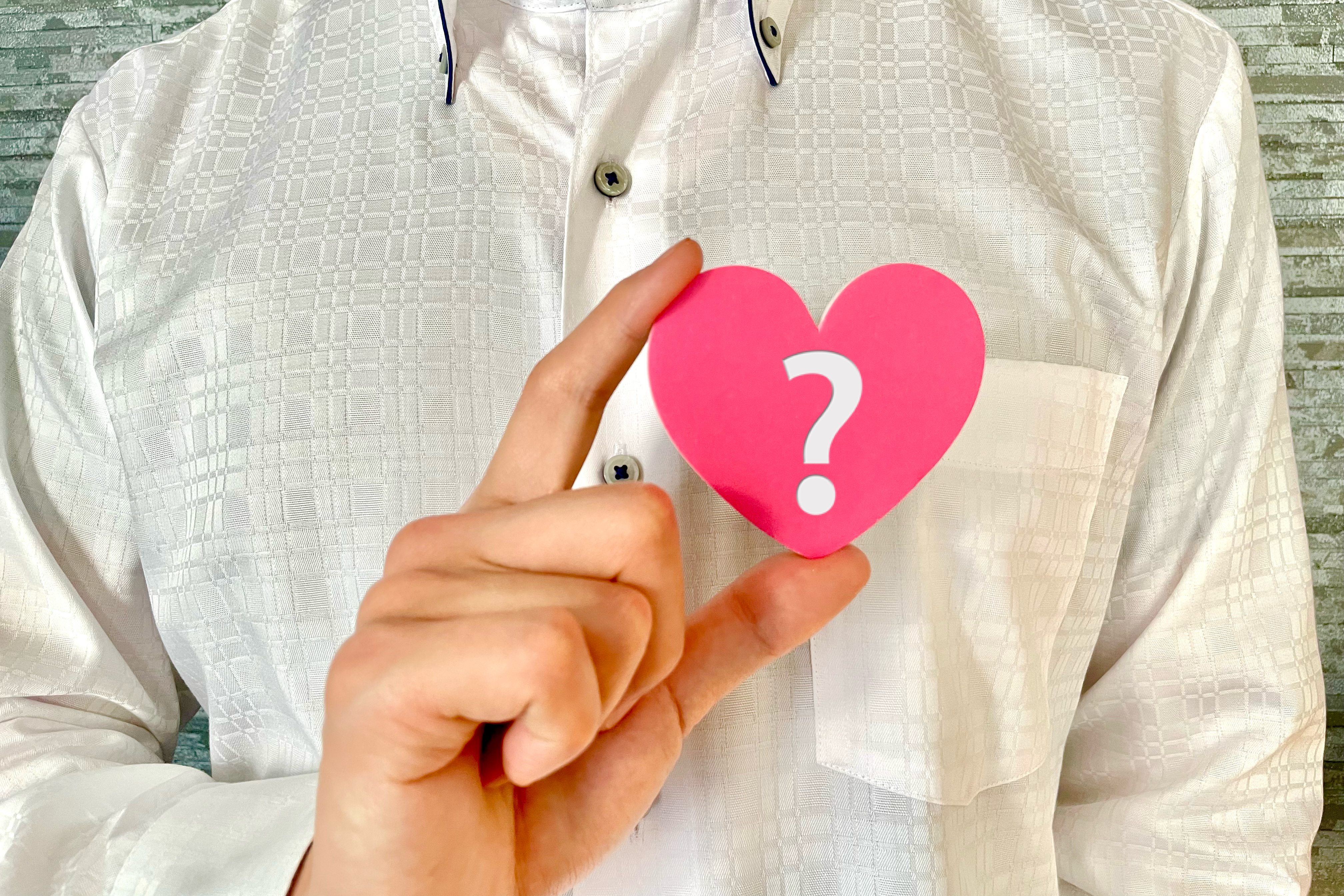
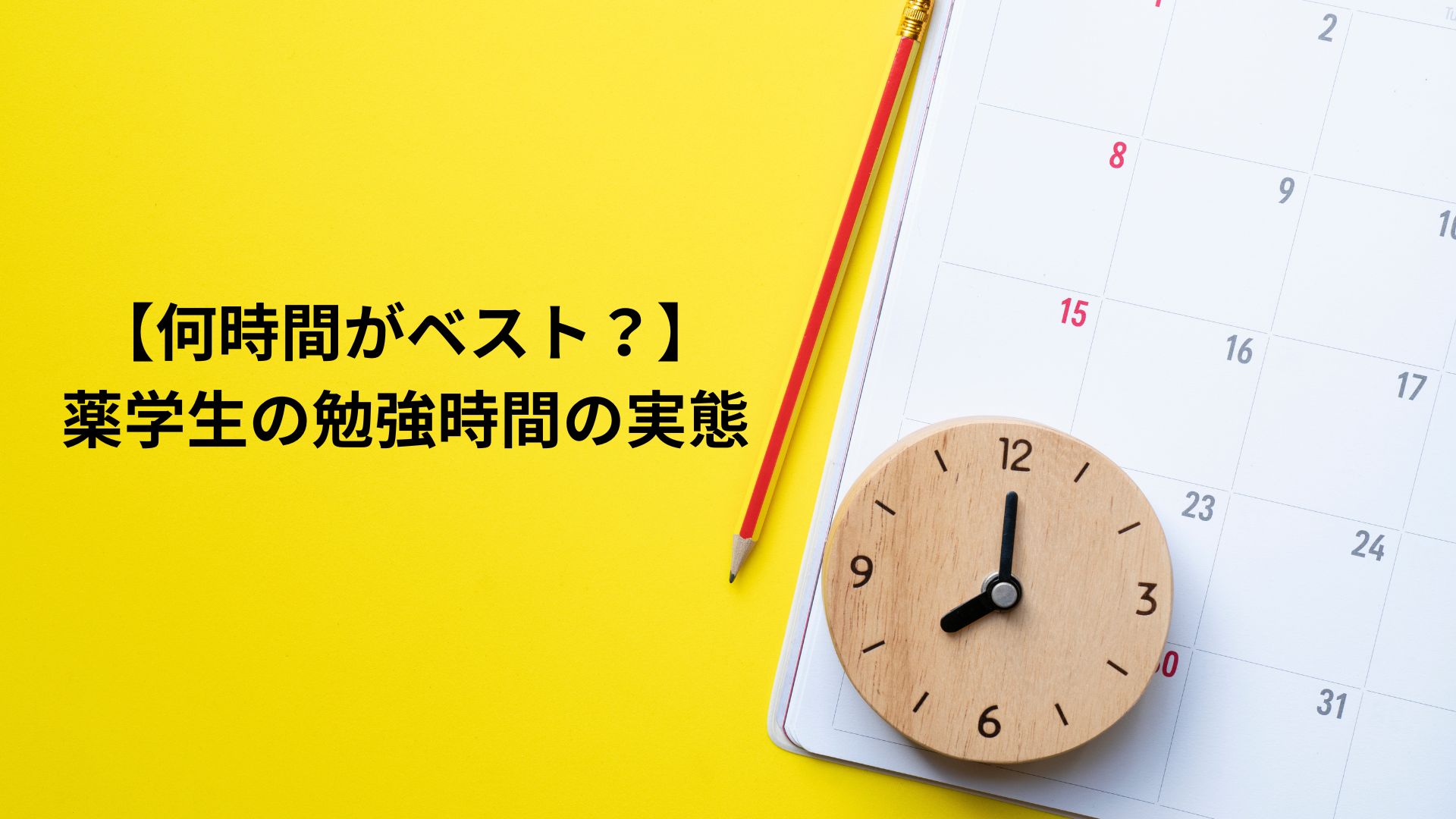

[…] 【薬学部】定期試験を余裕でパスする方法 ・試験には合格できるけどいつ… […]
[…] 試験に落ちる原因と成績が上がる勉強方法を徹底解説 […]
[…] ・薬剤師になるためには勉強をしなきゃいけない・そのために何を勉強するべきか・じゃあどうやって勉強していけばいいのか・そもそも薬剤師になりたい理由ってなんだっけ? […]
[…] 【薬学部】誰でもできる定期試験に受かるための勉強法 ・試験には合格で… 【国試一発合格】薬学生の勉強時間ってどれくらい?薬学生ってどれくらい勉強してるの?周りの人の勉強時間を参考にしたい。そう思っている方はこの記事を読んでみて下さい。… […]
[…] 【国試一発合格】薬学生の勉強時間ってどれくらい?薬学生ってどれくらい勉強してるの?周りの人の勉強時間を参考にしたい。そう思っている方はこの記事を読んでみて下さい。… 【薬学部】余裕を持って試験に合格するための勉強法 ・試験には合格でき… […]