【厳選】薬学生おすすめの参考書・問題集33冊

ハチです。
今回は、僕が実際に使った本の中で定期試験や国家試験に役に立った本を単元別に分かりやすく紹介していきます。
・薬学の本ってたくさんありすぎてどれがいいのか分からない
・実際どれがオススメなの?
という方はぜひ参考にしてみて下さい。
はじめに:スタンダード薬学シリーズがおすすめな理由
今回の記事ではスタンダード薬学シリーズをオススメしていることが多くなっています。
理由は、
・コアカリキュラム(コアカリ)に沿ってテキストが作られている
・基礎から国家試験レベルまで幅広くカバーされている。
・本にもよるが、問題数が豊富。
・図や表が見やすい。
この4点です。
中でも一番のメリットは問題数の多さです。
点数を上げるためにはたくさん問題を解くことが必須ですが、スタンダードシリーズは問題数が多いので力を付けるためにはもってこいの本です。
更に、スタンダードシリーズは1冊に問題と参考書が入っているので、問題を解いたらすぐに復習できるのもメリットです。
物理
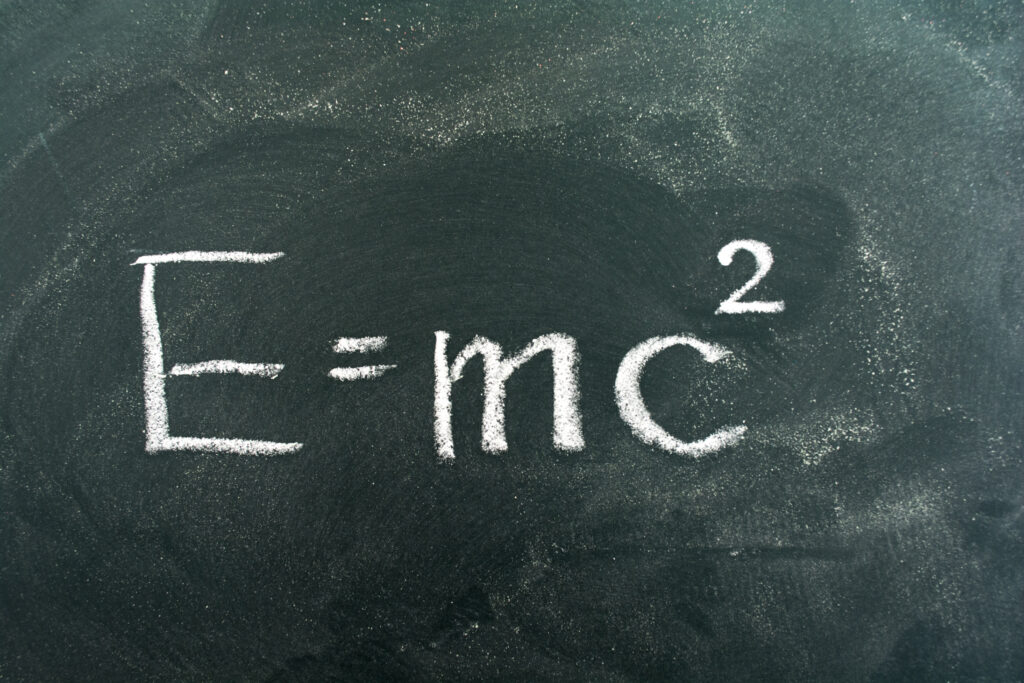
物理系薬学Ⅰ スタンダード薬学シリーズ
正直、スタンダードの物理は「国家試験超えてるんじゃない?」って程、問題の難易度が高いです。
でも、参考書としては非常に分かりやすいので普段の講義やテスト前の復習に最適です!
ざっくり、3冊で学べることをまとめると
Ⅰ:物理化学(放射線含む)、気体の状態、反応速度
Ⅱ:分析化学、酸塩基
Ⅲ:機器分析、構造決定(NMR等)
になります。
物理系薬学Ⅱ スタンダード薬学シリーズ
物理系薬学Ⅲ スタンダード薬学シリーズ
化学
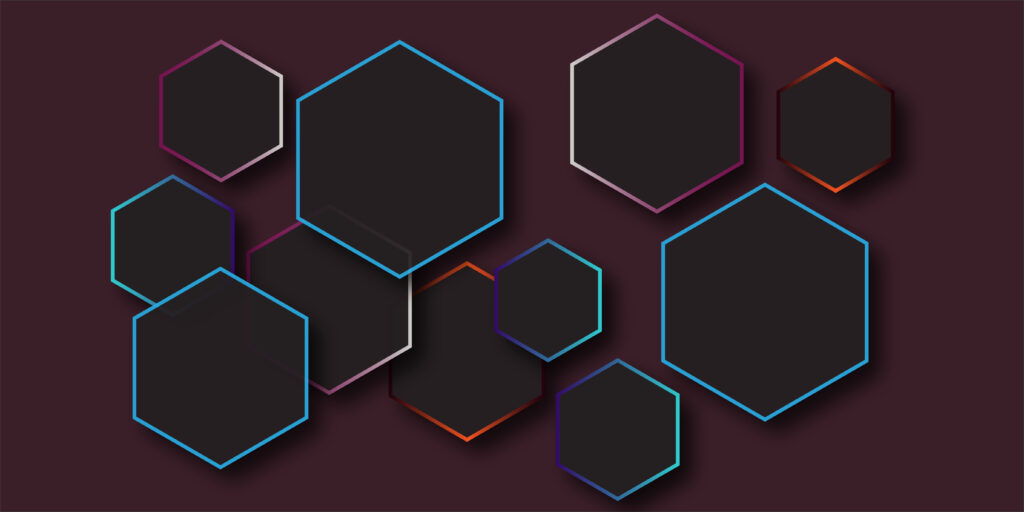
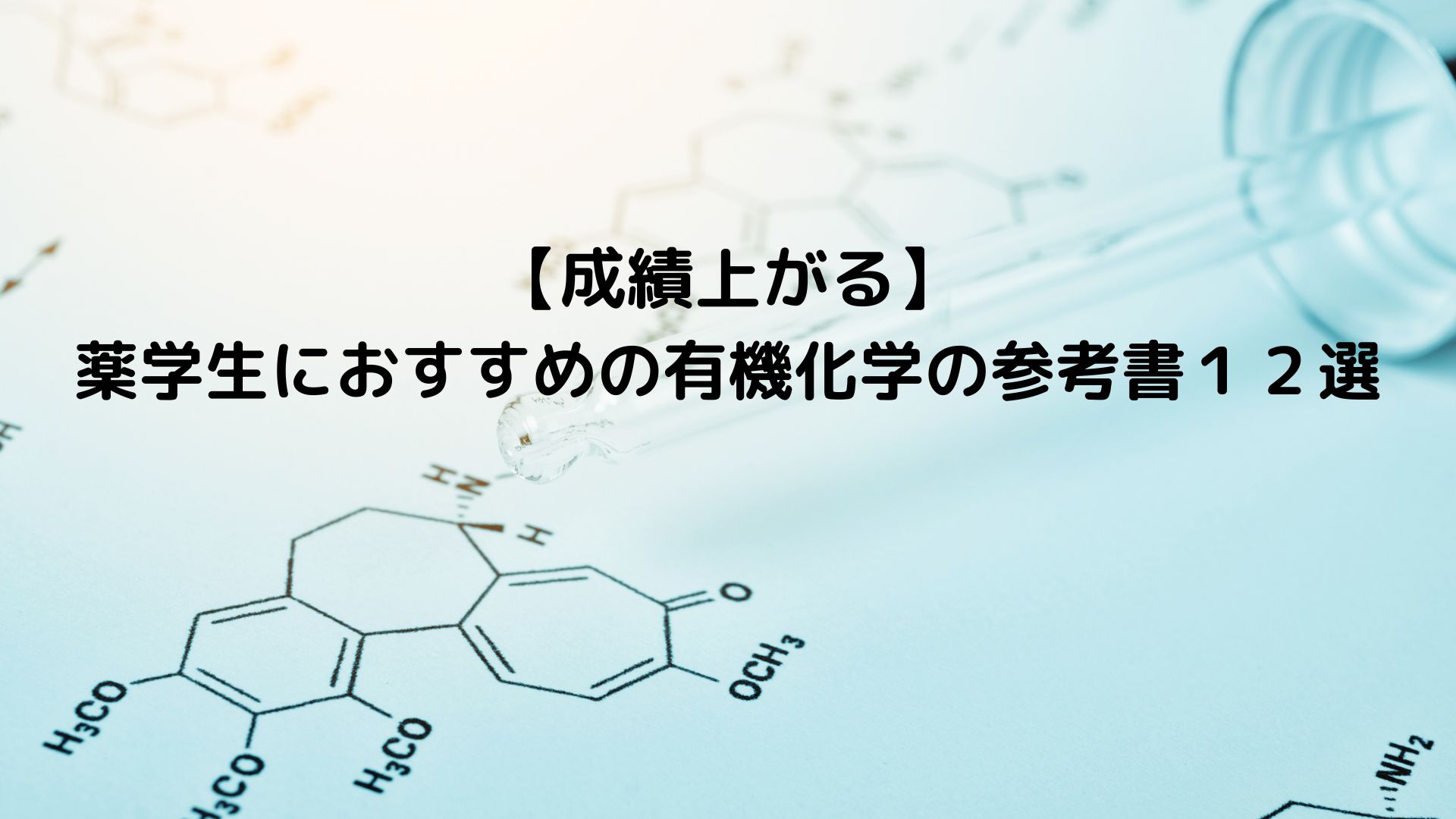
化学系薬学Ⅰ スタンダード薬学シリーズ
化学もスタンダードシリーズがオススメです。
3冊で学べることをざっくり解説すると、
Ⅰ:化学反応、官能基の性質、命名法
Ⅱ:医薬品化学
Ⅲ:生薬・天然物化学、構造決定
になります。
特に化学反応は、電子の動きが丁寧に書かれているので非常に分かりやすいです。
化学系薬学Ⅱ スタンダード薬学シリーズ
化学系薬学Ⅲ スタンダード薬学シリーズ
薬学生のための漢方薬入門
この本のすごいところが、漢方処方の解説が書かれていることです!!
簡単にいうと、その生薬が漢方薬でどんな働きをしているかが分かりやすく書いてあります。
漢方薬って、「葛根湯は風邪」みたいなイメージで覚えると思いますが、生薬の働きまでしっかり理解できるので漢方薬の理解に役に立つ1冊です。
他にも本書では、
・漢方の歴史
・漢方薬の処方(効能、副作用、相互作用など)
・生薬各論
・症例
が書かれています。
漢方薬全般について学びたい人にオススメ!
生薬単-語源から覚える植物学・生薬学名単語集
薬学生全員が持ってて欲しい!
と思っている本です。
・生薬の基原植物名
・基原植物の実際の写真
・薬用部位
・主要成分・構造式
・確認試験
・薬効
・漢方処方
これらがフルカラーで載っています!
フルカラーなので、実際の植物の色や形までイメージしやすくなっています。
個人的におもしろいなと感じたところは、
柑橘系の中でもCYP3A4を阻害するものと阻害しないものがある
という部分です。
つまり、CYP3A4で代謝されるCa拮抗薬などを飲んでいても食べても大丈夫な柑橘類がある!
ということです。
この知識があれば服薬指導などにも活かせそうですよね。
話が逸れましたが、良かったら読んでみて下さい!
生物

生物系薬学Ⅰ スタンダード薬学シリーズ
生物のスタンダードシリーズは問題数が他よりも圧倒的に多いので、中々覚えられない方には非常にオススメです。
生物は薬理学や病態など多くの分野を理解する土台の科目でもあるので、しっかり知識を付けるためにも本書を活用してみて下さい。
Ⅰ:生化学、分子生物学
Ⅱ:生理学
Ⅲ:免疫学・微生物学
各本の構成はざっくりこの通りです。
後述する病気がみえるシリーズと組み合わせると、疾患との関係性まで調べられるので組み合わせて勉強するとより知識が身に付きます。
本書で解剖や生理学が分かりずらければ、後述する病気がみえるシリーズを活用するのもアリです。
生物系薬学Ⅱ スタンダード薬学シリーズ
生物系薬学Ⅲ スタンダード薬学シリーズ
はたらく細胞
本ではないんですが、免疫・微生物の基礎を学びたい人にオススメのアニメです!
赤血球、白血球、B細胞、T細胞、マクロファージなど身体の中の細胞のはたらきについて楽しく学べます!
普通にアニメとしても面白いです。
U-NEXTなら31日無料で視聴できるので見てみて下さい!
(無料期間の途中で解約しても料金はかかりません)

衛生

スタンダード薬学シリーズ
これ1冊で衛生の全範囲をカバーすることができます!
ただ、問題数が少ないので次に紹介するパザパ薬学演習シリーズで問題を解いて本書で振り返る流れにするとグッドです。
パザパ薬学演習シリーズ
定期試験、CBT・国試対策はこの1冊と過去問でOKです。
前述したスタンダード衛生薬学と組み合わせて使うのがオススメです。
公衆衛生がみえる
・死因統計
・がんの有病率
・法律・制度
これらの情報は常に最新の情報を知っておく必要があります。
もちろん、スタンダード衛生薬学や青本などでもこれらの最新情報を扱っていますが、本書はイラスト付きで分かりやすく解説されています。
薬がみえるや病気がみえると同じシリーズだよ!
薬理

新図解表説薬理学・薬物治療学
・単元の初めに、関係する作用機序がすべて図で書かれていて見やすい
・成分名と商品名が書かれている
(例:アセトアミノフェン、カロナール®)
・付録には本書で扱っている医薬品の構造式が載っている
図解と書かれているだけあって、作用機序の図がとても分かりやすくて記憶に残りやすい!
更に成分名と一緒に商品名まで覚えられるので、実務実習や働いた後まで役に立ちます。
薬剤

薬の生体内運命 スタンダード薬学シリーズ
薬剤のスタンダードシリーズは問題数が少ないのがデメリットですが、問題を解くよりも過去問などでつまずいたところを見直すツールとして活用するのがオススメです。
薬剤は、暗記も多いですが計算や理解する部分が多いので講義などで分からなかった疑問を調べるために用いるのがいいです。
例えば、肝抽出率の計算が分からないと思った時に本書を見れば式の導き方や考え方までしっかりカバーすることができます。
製剤化のサイエンス スタンダード薬学シリーズ
病態・薬物治療
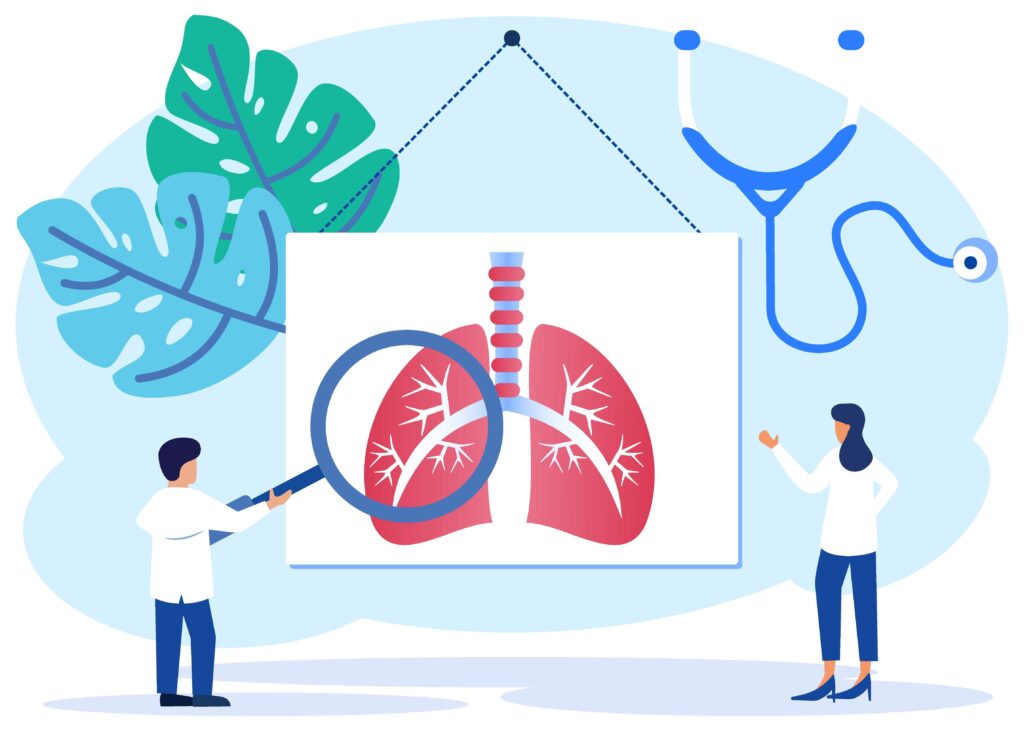
病気がみえるvol1:消化器
病態・薬物治療でオススメなのは、病気がみえるシリーズです。
(前述の公衆衛生がみえると同じシリーズです)
病気がみえるがオススメな理由は、
・解剖学や生理学、生化学が分かりやすく学べる
・病気の発生~対処までがイラスト付きで分かりやすく解説されている
・本書内のQRコードから心拍音が聴ける
などです。
とにかくフルカラー見やすい!
個人的な意見ですが、薬だけでなく病気もしっかり理解できていると視野が広くなるので患者さんにとって良いお薬が選べると思っています。
もちろん、医師のような知識を付けることは困難ですが、薬剤師なりに病気を理解することは大切かなと思います。
興味がある方は読んでみて下さい!
※Vol.11運動器・整形外科以外を購入しました
病気がみえるvol2:循環器
病気がみえるVol3:糖尿病・代謝・内分泌
病気がみえるVol4:呼吸器
病気がみえるVol5:血液
病気がみえるVol6:免疫・膠原病・感染症
病気がみえるVol7:脳・神経
病気がみえるVol8:腎・泌尿器
病気がみえるVol9:婦人科・乳腺外科
病気がみえるVol10:産科
病気がみえるVol12:眼科
病気がみえるVol13:耳鼻咽喉科
病気がみえるVol14:皮膚科
国家試験直前に役に立った本

ポイントブック 必須アドバンスト
国家試験直前に必ず活用して欲しい1冊です。
国試の過去問+オリジナル問題で合計300問が収載されていて、国試直前の力試しにもなります。
必須は足切りされたらそこで6年間が水の泡になってしますので、そうならないためにも活用してみて下さい。
薬剤師国家試験対策 必須問題集Ⅰ・Ⅱ
・必須問題に備えてとにかく問題を多くこなしたい
・色々な問題パターンに慣れておきたい
こういった方にオススメの本です。
国家試験の過去問+オリジナル問題で構成されていて、収載問題数はなんと2000問です!
僕の感想ですが、前述のポイントブックと本書をしっかりやれば必須対策は万全です!
Q&A
国家試験の対策は青本だけで十分じゃない?
もちろん、青本だけでも十分です!
でも、元々使っていたテキストがあればそれを使って国試対策した方が効率がいいです。
問題を解いたり講義を解いたりしてると、テキストに書き込みをする機会があります。
過去にテキストに同じような書き込みがしてあるのに、青本に改めて書き込みをすると時間の無駄になってしまします。
自分のテキストには書き込みをしている場合が多いので、新しく書き込みをする時間を省くためにも元から使っていたテキストで国試対策を行うといいです。
まとめると
国試対策を始める時に元から使用してたテキストがない⇒青本などを新しく購入
元から使用しているテキストがある⇒そのままテキスト使用
という流れになります。
低学年の内からスタンダードシリーズなどのテキストを購入して6年生になるまでに書き込みなどをしっかりしておくと、それだけで周りと差が付きます。
まとめ:気になった参考書があれば活用してください
ここまで33の参考書を紹介してきましたが、迷ったら、スタンダードシリーズと病気がみえるシリーズは間違いないので活用してみて下さい!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
みなさんのオススメ参考書も教えていただけると嬉しいです!





































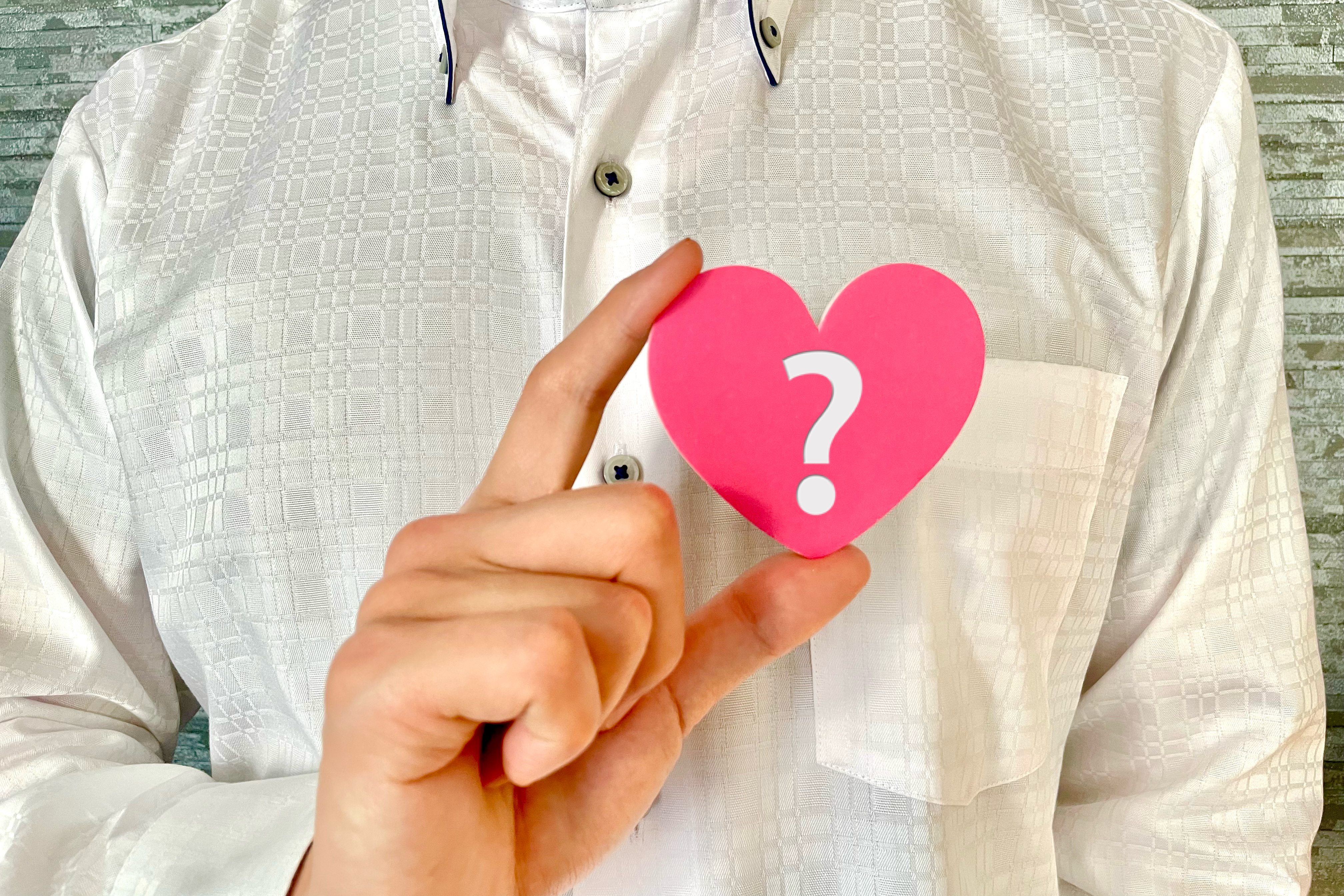
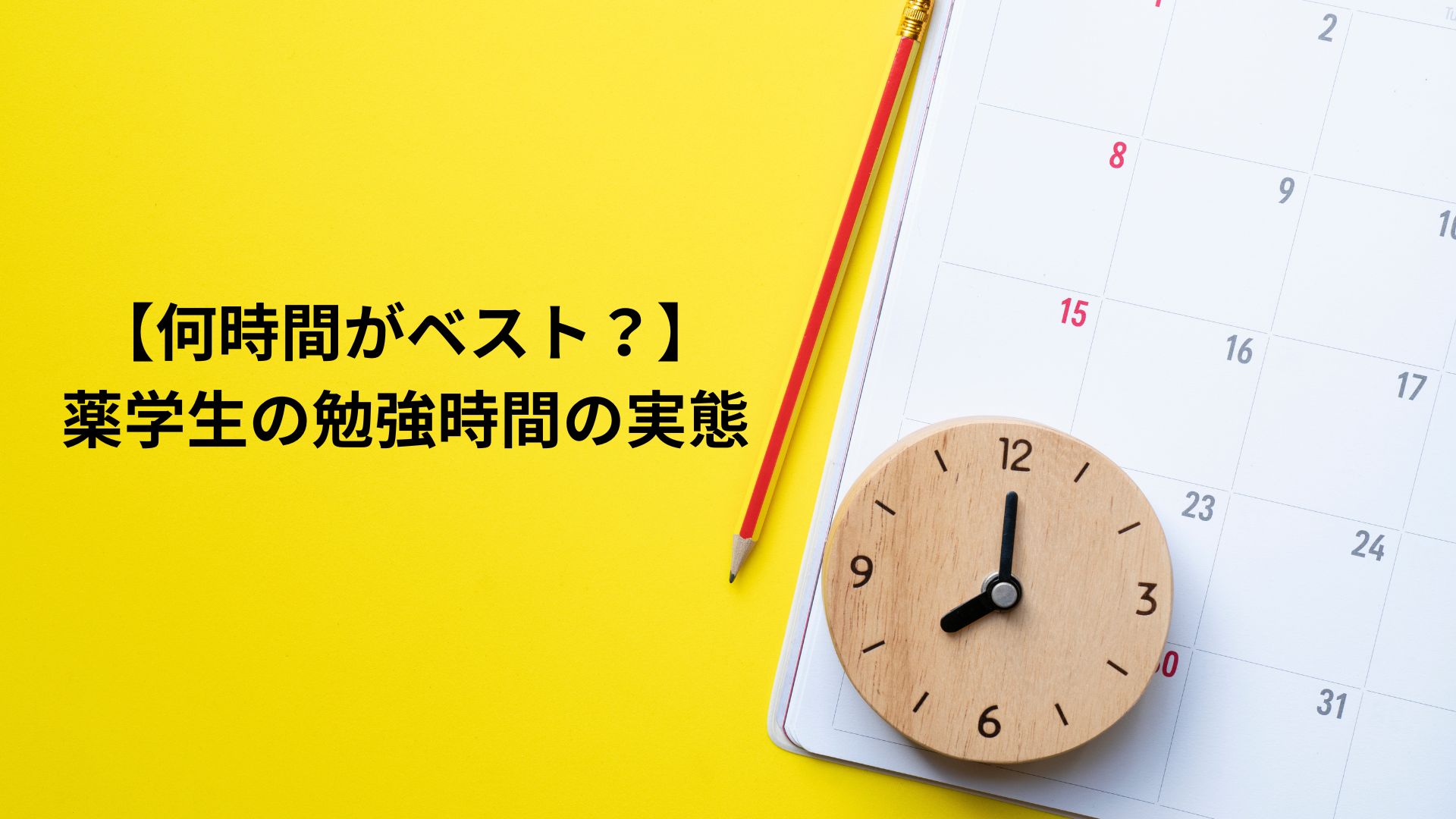

[…] あわせて読みたい【厳選】薬学生おすすめの参考書・問題集33冊 あわせて読みたい【1年で70点UP】薬剤師国家試験の勉強方法を5ステップで解説 […]
[…] […]
[…] ・関連する国家試験の過去問・その他問題集 […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]