【薬学生向け】定期試験・国家試験の過去問活用法
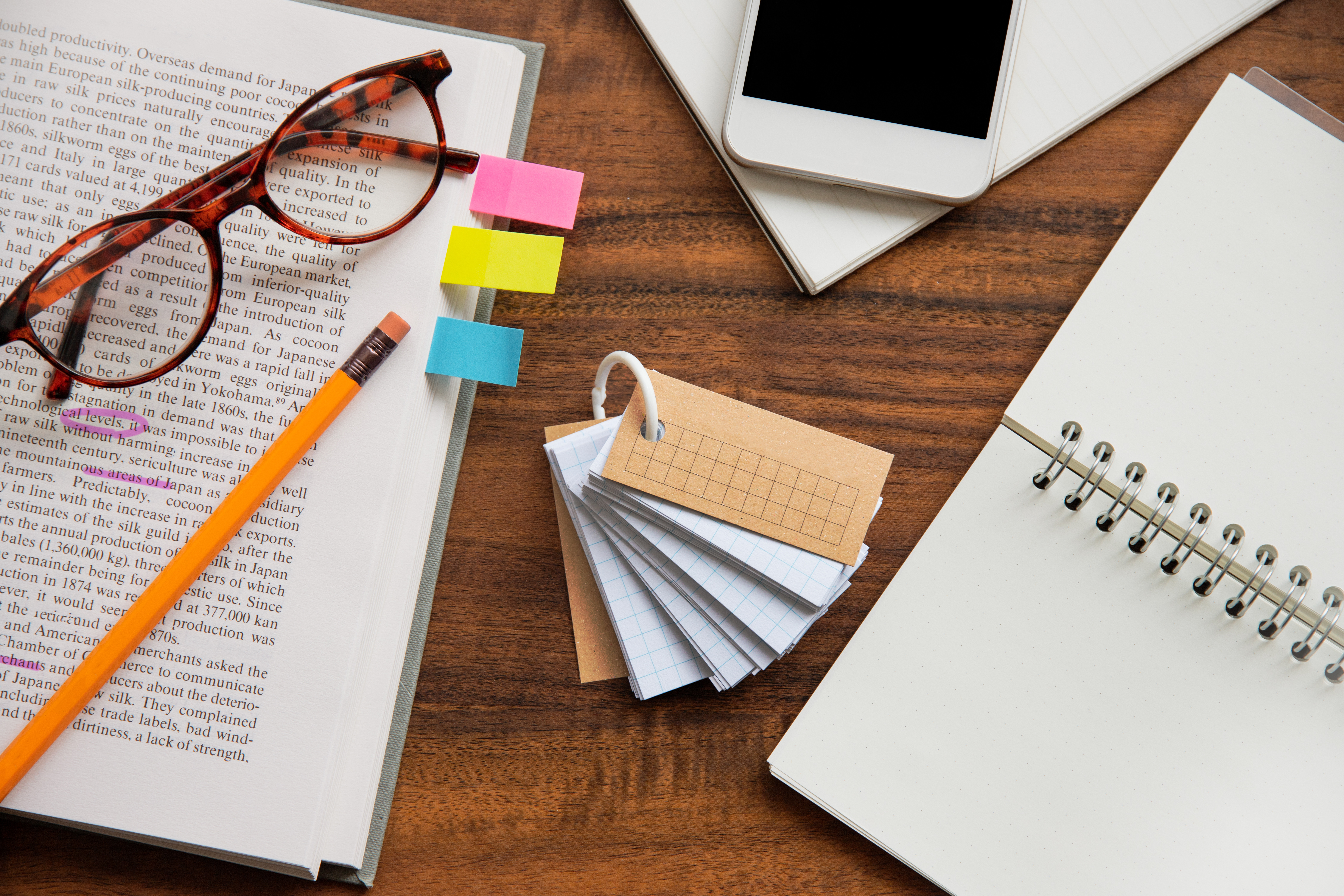
ハチです。
・過去問やらないと国試受からないよ。
・過去問やっておけばとりあえず大丈夫だから!
こんなことをよく耳にしますが、正直過去問を解いただけで試験に合格するのは難しいです。
理由は、過去問の分析ができていないからです。
具体的には、
・選択問題なのか、記述式なのか。
・どの辺りが問われやすいのか。
・どこを勉強すればいいのか。
この辺りを把握せずに試験を受けるから、不合格になってしまいます。
僕も成績が悪かった時は過去問を解くだけになっていましたが、過去問分析を始めてからは試験で点数を取れるようになりました。
今回の記事では、そんな過去問分析の方法を定期試験と国家試験の2パターンに分けて解説していきます。
・過去問の使い方を具体的に知りたい
・次の定期試験がすごく不安
・国家試験の範囲が広すぎて何から勉強したらいいのか分からない
このような方はぜひ参考にしてください。

過去問をやる理由は勉強に優先順位をつけるため
過去問分析なんてめんどくさいことしないで全部覚ればいいじゃん!
って思ったかもしれませんが、全てにおいて100点を取るのは無理です。
単純に時間が足りないからです。
限られた時間の中で合格点に達する必要があるので、勉強に優先順位を付ける必要があります。
その優先順位を付けるためには、自分が受験する試験がどういうものなのかを知る必要があります。
過去問は「試験の情報そのものが詰まっているツール」なので、これを使わない手はないです。
過去問はゲームの攻略本みたいな感じだね!
【定期試験版】過去問分析の手順
定期試験の過去問の使い方を解説していきます。
1.出題形式を把握する
まずは、過去問を見て
・選択式?記述式?
・問題数、試験時間
この辺りを確認しましょう。
また、選択式と記述式が混ざっている時はどれくらいの割合で出題されているのかまでチェックすると勉強の計画が立てやすいです。
2.毎年問われているところを書き出す
過去問を数年分見ていると、毎年問われている分野があるはずです。
そこをノートや紙に書き出しましょう。
同じ問題が出題されることはあまりないので、ざっくり同じような分野が問われていたらメモしましょう。
当たり前ですが、毎年出題されている分野は今回も出題される可能性が高いです。
書き方の例はこんな感じです。
薬理学Ⅰ 2020~2022過去問 毎年出題されているところ
〇アドレナリン作動薬
〇抗コリン薬
〇受容体の伝達経路(記述)
記述式で問われてたところは、メモを残しておくと、見返した時に分かりやすいです。
3.その他問われている部分を書き出す
毎年問われている分野が把握できたら、次はそれ以外で出題されている分野を書き出します。
毎年出ているところより重要度は下がりますが、それでも一度は出題されているのでテスト前に見直しておくのがいいです。
4.毎年出題分野→その他の順で勉強する
出題傾向が把握できたら、いよいよ知識のインプットに取り掛かります。
勉強の順番は、
毎年問われている分野
↓
その他の分野
の順で、優先順位が高いものから勉強していくのがオススメです。
基本的に講義資料や教科書を中心に勉強するのが普通ですが、余裕があれば
・関連する国家試験の過去問
・その他問題集
まで解いて準備しておくと万全です。
僕個人の意見ですが、国家試験を参考に試験を作る先生は多いと思います。
【国家試験版】過去問分析の手順
国家試験は定期試験と違って試験範囲が膨大なので、過去問分析のやり方を少し変えて解説します。
国家試験の詳しい勉強方法についてはこちらの記事で解説しています!

1.過去問を解いて自分の実力を把握する
まずは、直近1年分の過去問を解いて自分の実力を把握しましょう。
点数など把握するべき項目は幾つかありますが、ここで一番重要なのは自分が正答率60%の問題がどれくらい解けているかです。
理由は、
正答率60%以上の問題を全て解ければ合格点に達するからです。
これは、過去の国家試験のデータが証明している事実です。
勉強が苦手な方や中々点数が取れない方は、この辺りの問題がちゃんと解けているかの確認が最優先になります。
2.正答率60%以上の問題を書き出す
前述した、正答率60%以上かつ解けなかった問題を書き出します。
書き方の例です。
108回過去問
問2 全部
問9(選択肢4のみ)
問22 (選択肢2,5)
このメモは後から振り返ることができるので、残しておくのがオススメです。
余談ですが、必須問題は正答率に関わらず全部できるようにしておくと基礎固めになります。
3.正答率60%以上の問題+その周辺を勉強する
正答率60%以上の問題
↓
その周辺の分野の勉強※
の順で勉強をしていきます。
※周辺の分野とは、正答率60%以上の問題で出題された分野の周辺という意味です。
例えば、
アトロピンの構造が出題された⇒他の天然物の構造が問われる可能性がある
と考えて、アトロピン周辺を勉強するイメージです。
国家試験で同じ問題は出題されませんが、似た問題(過去問で出た分野周辺)が出題されるので、過去問の周辺まで見ておくことが大切です。
4.その他の分野に取り組む
上記の勉強が終わったら、その他の正答率が60%未満の問題に取り組みましょう。
やり方は先程と同じで、選択肢の理解+周辺の勉強です。
Q&A
Q1.過去問がない試験の対処法を教えて下さい。
個人的には過去問がない試験の方が少ないと思いますが、もし過去問がない場合の対処法として参考にしてください。
・先輩にどんな感じの試験だったか聞く
・友人と問題を作り合う
・講義のポイントを元に関連する国試の過去問を解く
辺りが試験対策になると思います。
過去問がない試験はどうしても勉強の効率が落ちるので、周りと協力しながら勉強を進めていけたらベストです。
Q2.テスト勉強は何から始めればいいですか?
過去問分析から初めて試験の傾向を知ろう!
過去問分析をやる時期は、試験直前だとバタバタするので講義中間(7~8回目)辺りで始めると良いと思います。
過去問分析は早くやるほど、勉強の計画を立てやすくなるので新学期が始まったら早めに過去問を入手しましょう!
勉強は過去問分析を早く始めた者勝ち!
Q3.過去問は何年分やればいいですか?
定期試験なら3年分以上
国家試験なら5年分以上
あくまで目安ですが、参考にしてください。
因みに僕は106回受験でしたが、過去問は96回~105回を3週ずつくらいやりました。
Q4.記述対策を教えてください。
ポイントはこの3点です。
・過去問の答えを暗記しない
・文章のポイントを押さえて、自分の言葉で表現するトレーニングをする
・「なにがどうなってどうなった」を意識して文章を作る
結局、「どう書いたら相手に伝わるかな?」を考えて文章を作らないと点数に繋がらないし、患者さんに伝えたいことが伝わらなくなってしまいます。
まとめ:過去問を制する者は勉強を制する
繰り返しになりますが、過去問をやる理由は勉強に優先順位をつけるためです。
無限に時間があれば優先順位をつける必要はないですが、試験までの時間は限られています。
過去問分析のおさらいです。
1.出題形式を把握する
2.毎年問われているところを書き出す
3.その他問われている部分を書き出す
4.毎年出題分野→その他の順で勉強する
1.過去問を解いて自分の実力を把握する
2.正答率60%以上の問題を書き出す
3.正答率60%以上の問題+その周辺を勉強する
4.その他の分野に取り組む
しっかり過去問に取り組むと膨大な時間がかかりますが、その分やる価値があります。
過去問を上手に活用して、効率よく点数を上げていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。




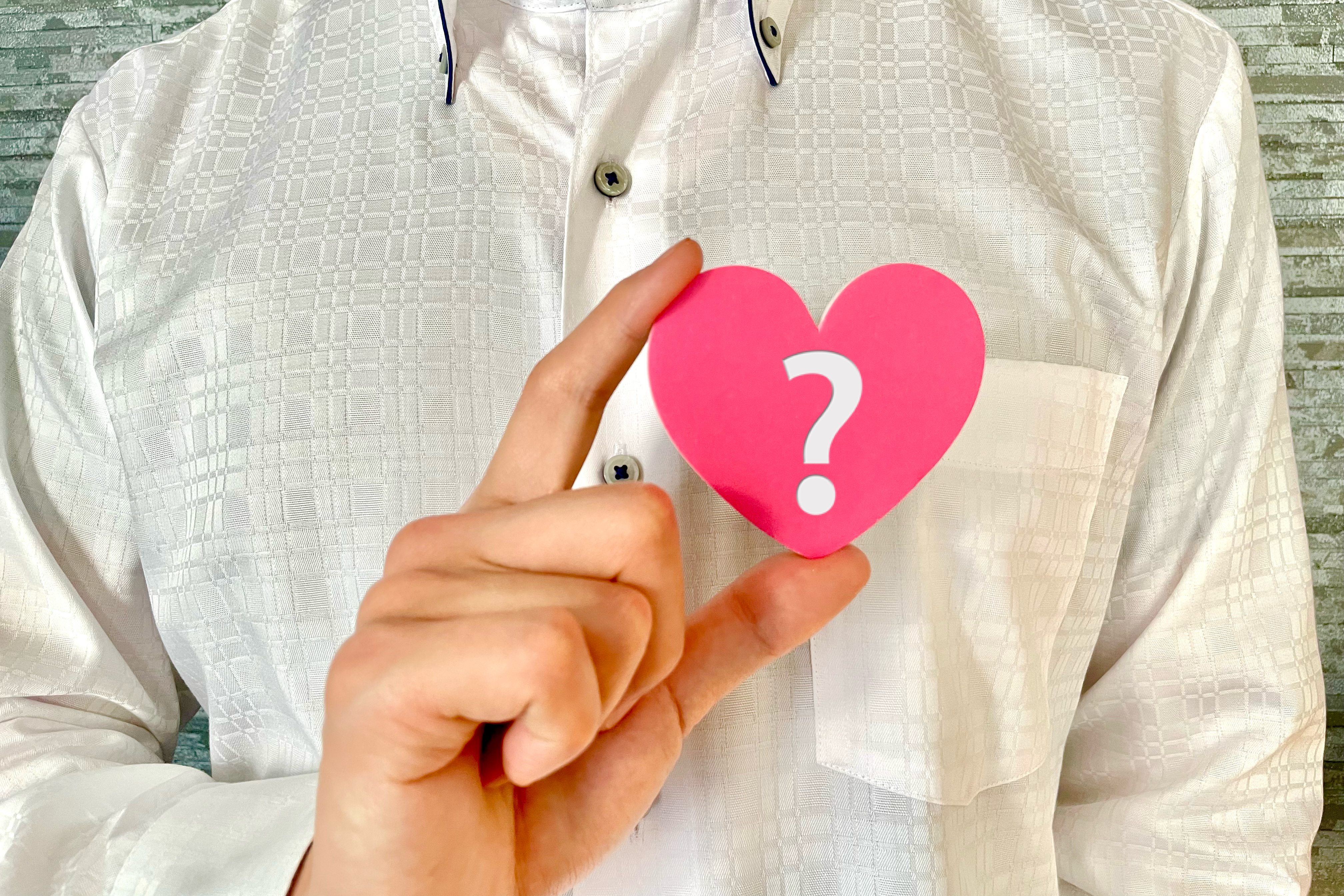
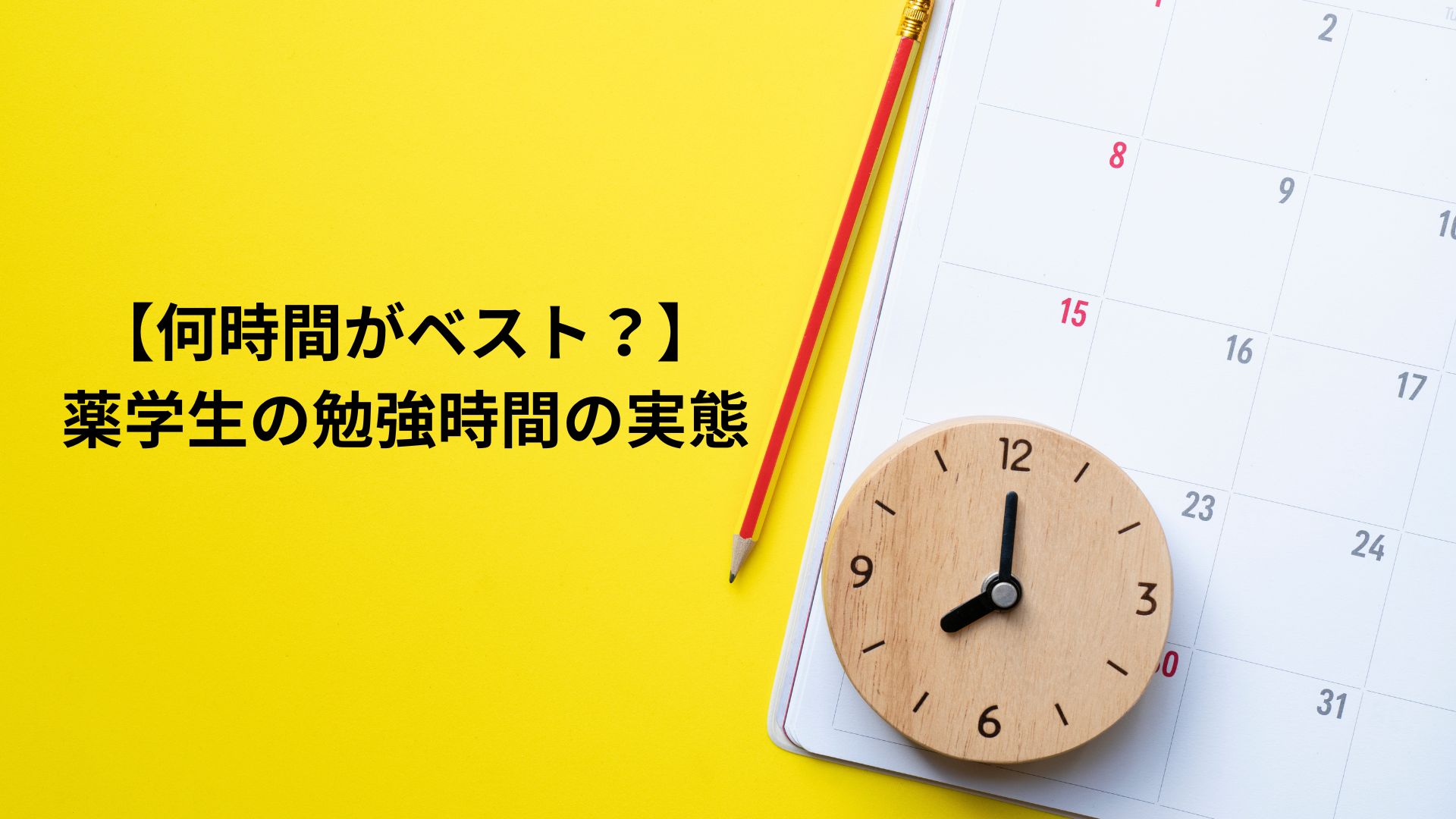

[…] あわせて読みたい【薬学生向け】定期試験・国家試験の過去問活用法 […]
[…] […]